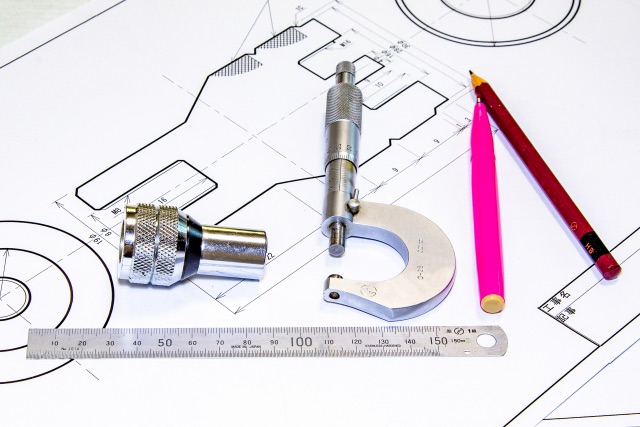はじめに
設変とは「設計変更」の略称で、製造業では日常的に使われる重要な用語です。特に「メジャー設変」と「マイナー設変」という言葉は、設計部門だけでなく、生産管理、品質管理、営業、調達など様々な部門で頻繁に使用されます。
この記事では、メジャー設変とマイナー設変の基礎知識から実務での扱い方まで、わかりやすく解説します。
「設計変更」とは
設計変更の定義
設計変更とは、製品の図面や仕様書などの設計情報を変更することを指します。製造業において、製品は一度設計したら終わりではありません。品質改善、コスト削減、法規制への対応、市場ニーズの変化など、様々な理由で設計を変更する必要が生じます。
なぜ設計変更が必要なのか
製造業における設計変更の主な理由には、以下のようなものがあります。
品質向上のため
製品を市場に出した後、顧客からのフィードバックや市場での不具合情報をもとに、より品質の高い製品へと改良していきます。例えば、ある部品の強度不足が判明した場合、材質を変更したり、形状を見直したりする必要があります。
コスト削減のため
より安価な材料への変更や、製造工程の簡略化によって、製品のコスト競争力を高めることができます。ただし、品質を維持しながらのコスト削減が大前提となります。
法規制への対応
環境規制や安全基準の変更に伴い、使用できる材料や部品が制限されることがあります。例えば、RoHS指令のような有害物質規制により、特定の材料を使用できなくなった場合、代替材料への変更が必要です。
部品の生産終了への対応
サプライヤーが部品の生産を終了する場合、代替部品への変更が必要になります。特に電子部品などは製品ライフサイクルが短く、このような変更が頻繁に発生します。
メジャー設変とは?-品番や図面番号そのものが変更される
メジャー設変の定義
メジャー設変(Major Change)とは、製品の機能や性能、安全性に大きな影響を与える設計変更のことを指します。この場合、設変の前後で製品そのものに大きな変更が加えられるため、品番も合わせて変わります。
メジャー設変の具体例
製品の基本性能に関わる変更
出力性能の向上、処理速度の変更、容量の増減など、製品のカタログスペックに影響する変更です。例えば、モーターの出力を50Wから100Wに変更する場合、これは明らかにメジャー設変となります。
安全性に関わる変更
安全装置の追加や変更、耐久性に影響する部材の変更など、製品の安全性に関わる部分の変更は、必ずメジャー設変として扱われます。
外観や寸法の大幅な変更
製品の外形寸法が変わると、顧客の設置環境に影響を与えます。また、外観デザインの大幅な変更も、ブランドイメージや市場での認知に影響するため、メジャー設変として扱われることが多いです。
主要部品の変更
製品の心臓部となる重要な部品の変更、例えば制御基板全体の刷新や、エンジンの型式変更などは、メジャー設変に該当します。
材質の変更で特性が大きく変わる場合
金属からプラスチックへの変更や、異なる材質への変更で強度や耐熱性などの特性が大きく変わる場合は、メジャー設変となります。
メジャー設変の手続きと影響
メジャー設変を実施する際には、通常以下のような厳格な手続きが必要です。
設計審査の実施
複数の部門が参加する設計審査会(デザインレビュー)を開催し、変更内容の妥当性を多角的に検証します。設計部門だけでなく、品質保証、生産技術、購買、営業など、関連する全ての部門が参加することが一般的です。
試作と評価試験
変更後の設計で試作品を製作し、性能試験、耐久試験、安全性試験など、必要な評価試験を実施します。この試験には数週間から数ヶ月かかることもあります。
承認プロセス
部門長や事業部長、場合によっては経営層の承認が必要となります。承認には詳細な変更内容の説明資料や、試験結果のデータが求められます。
顧客への通知
製品の性能や仕様に影響がある場合、顧客に事前に通知し、承認を得る必要があります。特にBtoB(企業間取引)では、顧客側でも評価試験が必要になることがあり、実施までに長い期間を要します。
品番や図面番号の変更
メジャー設変では、製品そのものに大きな変更が加えられるため、品番や図面番号の変更が行われることが一般的です。これにより、変更前後の製品を明確に区別できるようにします。
製造ラインの変更
製造工程や検査方法の見直しが必要になることも多く、作業者への教育訓練も実施します。
マイナー設変とは?-改訂履歴や設変符号のみが更新される
マイナー設変の定義
一方の、マイナー設変(Minor Change)は、製品の機能や性能、安全性に直接的な影響を与えない軽微な設計変更のことを指します。
マイナー設変の具体例
同等品への部品変更
同じ規格で同等の性能を持つ部品への変更です。例えば、同じ抵抗値を持つ抵抗器をメーカーAからメーカーBの製品に変更する場合などです。
外観上の軽微な変更
機能に影響しない表面処理の変更や、目立たない部分の色の変更などです。例えば、内部構造の塗装色を変更しても、製品の性能には影響しません。
製造方法の変更(性能に影響がない範囲)
ボルトの締め付け順序の変更や、組み立て工程の効率化など、最終的な製品性能に影響を与えない製造方法の変更です。
図面表記の修正
寸法の許容差の表記方法の変更や、図面上の注記の追加・修正など、実際の製品には変更がない場合です。
材料の規格変更(同等品質)
材料メーカーが規格番号を変更したが、実質的に同じ材料である場合などです。
マイナー設変の手続きと影響
マイナー設変の手続きは、メジャー設変に比べて簡略化されています。
簡易的な審査
関連する部門の担当者レベルでの確認で済むことが多く、大規模な設計審査会は不要です。
限定的な評価
変更箇所に関する簡易的な確認試験を実施しますが、全ての性能試験をやり直す必要はありません。
承認の簡略化
課長や部長レベルの承認で対応できることが多く、経営層の承認は通常不要です。
顧客への通知は限定的
性能や仕様に影響がないため、顧客への事前通知が不要な場合もあります。ただし、取引契約によっては全ての変更を通知する義務がある場合もあります。
改訂履歴や設変符号のみ変更
品番や図面番号そのものは変更せず、図面の「改訂履歴」や、品番の末尾に付与される「設変符号」のみを更新することが一般的です。
メジャー設変とマイナー設変の判断基準
判断基準の重要性
設計変更がメジャーなのかマイナーなのかを正確に判断することは、非常に重要です。万が一、本来メジャー設変として扱うべきものをマイナー設変として処理してしまうと、十分な評価が行われず、品質問題や安全上の問題が発生する可能性があります。逆に、マイナー設変で済むものをメジャー設変として扱うと、不必要なコストと時間がかかり、業務効率が低下します。
一般的な判断基準
多くの企業では、以下のような項目を判断基準として設定しています。
形態への影響
製品の外形寸法、重量、外観に変更があるか。変更がある場合、その程度はどの程度か。
適合性への影響
法規制や業界規格への適合性に影響があるか。認証の取り直しが必要になるか。
機能への影響
製品の基本機能や性能に変更があるか。カタログスペックに影響するか。
互換性への影響
従来品との互換性が維持されるか。顧客の使用環境で問題が生じないか。
信頼性への影響
製品の耐久性や信頼性に影響があるか。故障率に変化が生じる可能性はあるか。
設計変更管理の実務
設計変更の流れ
実際の業務における設計変更は、一般的に以下のような流れで進められます。
変更の提案・発議
設計変更の必要性が認識されたら、変更依頼書や変更提案書を作成します。変更理由、変更内容、期待される効果などを明確に記載します。
影響範囲の調査
変更によって影響を受ける図面、部品、工程などを洗い出します。これを「影響範囲調査」や「影響度評価」と呼びます。
メジャー/マイナーの判定
前述の判断基準に基づいて、メジャー設変かマイナー設変かを判定します。この判定は、品質保証部門や設計管理部門が行うことが一般的です。
必要な評価・試験の実施
判定結果に応じて、必要な評価試験を計画・実施します。
承認プロセス
所定の承認者から承認を取得します。電子承認システムを使用している企業も多くなっています。
関連文書の改訂
図面、仕様書、作業指示書、検査基準書など、関連する全ての文書を改訂します。
関係部門への展開
製造部門、品質保証部門、購買部門など、関係する全ての部門に変更内容を通知し、必要な準備を依頼します。
変更の実施
実際に変更を実施します。旧仕様から新仕様への切り替えタイミングの管理が重要です。
効果の確認
変更実施後、期待した効果が得られているかを確認します。
設計変更管理で重要なポイント
トレーサビリティの確保
いつ、誰が、なぜ、どのように変更したのかを明確に記録し、追跡可能にしておくことが重要です。これは、後で問題が発生した際の原因究明や、同様の変更を検討する際の参考情報として活用されます。
在庫部品の管理
設計変更を実施する際、旧仕様の部品在庫をどうするかは重要な検討事項です。在庫を使い切ってから新仕様に切り替えるのか、在庫を廃棄して即座に切り替えるのか、コストと品質のバランスを考慮して判断します。
市場在庫への対応
すでに市場に出荷された製品や、流通在庫がある場合、それらをどう扱うかも検討が必要です。特に安全性に関わる変更の場合、リコールや改修作業が必要になることもあります。
文書管理の徹底
改訂前の図面や仕様書も、一定期間保管しておく必要があります。過去に製造した製品の修理やメンテナンスで、旧仕様の情報が必要になることがあるためです。
デジタル化と設計変更管理
PLM・PDMシステムの活用
現代の製造業では、PLM(Product Lifecycle Management:製品ライフサイクル管理)やPDM(Product Data Management:製品データ管理)といったシステムを使って設計変更を管理する企業が増えています。
これらのシステムを使うと、設計変更の履歴が自動的に記録され、関連する図面や文書が一元管理されます。また、承認フローも電子化され、進捗状況がリアルタイムで把握できるようになります。
BOM(部品表)管理との連携
設計変更は必ずBOM(Bill of Materials:部品表)の変更を伴います。システム上でBOMと設計変更を連携させることで、変更による部品の追加・削除・変更が自動的に反映され、管理の精度が向上します。
実際のケーススタディ
ケース1:メジャー設変の例
あるエレ機器メーカーで、製品の制御用マイコンを新型に変更することになりました。新型マイコンは旧型より高性能で、消費電力も少ないという利点がありました。
しかし、この変更によって制御プログラムの全面的な書き換えが必要となり、基板のパターンも変更が必要でした。製品の性能にも影響があるため、これはメジャー設変として扱われました。
開発期間は6ヶ月、各種評価試験に3ヶ月かかりましたが、結果として製品の競争力が大幅に向上しました。
ケース2:マイナー設変の例
同じメーカーで、製品ケースに使用するボルトのメーカーを変更することになりました。従来のサプライヤーが生産終了を発表したためです。
新しいボルトは、JIS規格で定められた同じ規格品で、強度や寸法も同等でした。組み立て方法にも変更はありません。そのため、これはマイナー設変として処理されました。
同等品であることの確認と簡易的な組み立て試験のみで、2週間で変更が完了しました。
ケース3:判断を誤ったケース
あるケースでは、樹脂部品の材料変更をマイナー設変として処理しました。材料メーカーからは「同等品」という説明を受けていたためです。
しかし、実際に製品を使用すると、高温環境下で変形が発生することが判明しました。新材料は、カタログ上のスペックは同等でしたが、長期的な耐熱性に問題があったのです。
結果として、市場からの回収と部品交換が必要となり、多大なコストと信用低下を招きました。本来は十分な評価試験を実施すべきメジャー設変として扱うべき案件でした。
まとめ
製造業における設計変更は、製品の品質向上、コスト削減、市場競争力の維持に欠かせない業務です。メジャー設変とマイナー設変を正しく理解し、適切に管理することが、製品の品質と企業の信頼性を守ることにつながります。